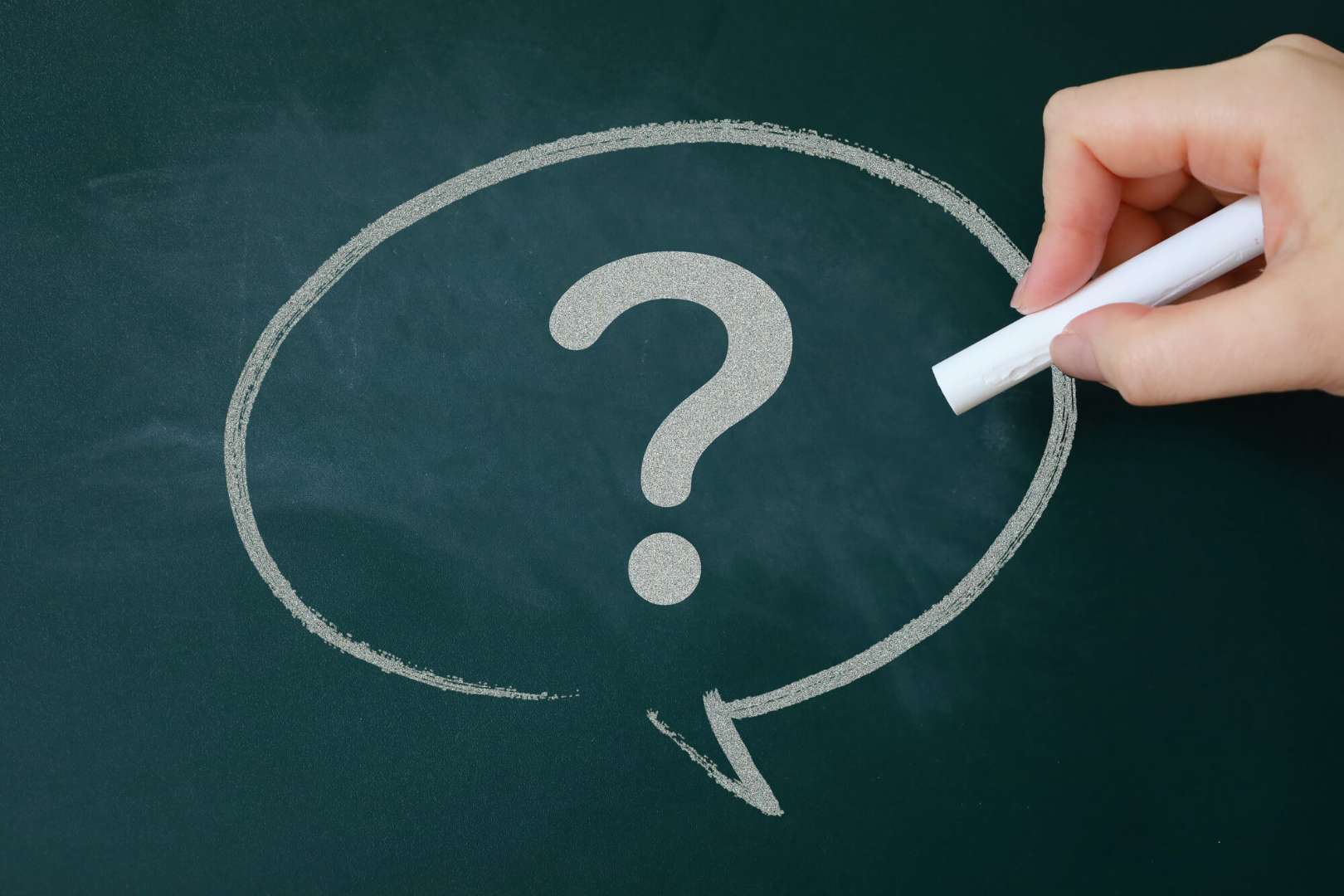電気工事士には「第一種」と「第二種」がありますが、「どちらを取ればいいのか」という悩みは、資格取得を考える人の多くがぶつかる最初の壁です。一種のほうが上位資格とされているものの、実際の現場では二種で十分対応できる仕事も多く、必ずしも上を目指せばいいという話ではありません。
たとえば、住宅のリフォームや店舗の電気工事を中心とする仕事であれば、第二種でほぼカバーできます。一方、工場やマンションの共用部、高圧設備などを扱う職場では、第一種が必要になる場面も出てきます。
資格選びで大切なのは、自分がどんな現場で働きたいのかを具体的にイメージすること。仕事内容やキャリアの方向性によって「最初に取るべき資格」は変わります。次のセクションでは、この判断の土台となる資格制度の違いを、制度面から整理していきます。
試験の内容・受験資格・工事範囲…制度的な違いをわかりやすく解説
電気工事士の第一種と第二種には、制度として明確な違いがあります。まず対応できる工事範囲についてですが、第二種は一般住宅や店舗などの「一般用電気工作物」を扱うための資格です。対象となるのは600ボルト以下の低圧回路で、照明・コンセントの配線、分電盤の設置といった家庭用電気設備が中心です。
一方、第一種はそれに加え、マンションの共用設備や工場の動力設備など「自家用電気工作物」にも対応可能です。ここでは600ボルトを超える高圧設備の扱いや、受変電設備の保守など、より専門性と責任が求められる業務が含まれます。
試験制度も異なります。第二種は年齢や実務経験に制限がなく、誰でも受験可能ですが、第一種は免状交付時に5年程度の実務経験が求められます(または免除条件あり)。試験の内容も第一種のほうが難易度が高く、特に筆記では高圧機器や系統保護に関する出題が加わります。
とはいえ、初学者にとっては第二種から始めた方がスムーズに理解できるケースが多く、いきなり第一種を目指すより、実務を重ねながら段階的にステップアップするほうが現実的です。次のセクションでは、こうした工事範囲の違いが、実際の仕事や役割にどう影響するかを掘り下げていきます。
一種を持つとできる仕事は?職場での役割や責任の違いに注目(第3セクション・700文字)
資格の違いは、そのまま現場での「できること」と「任される範囲」に直結します。第二種を持っていれば、戸建て住宅の電気配線、エアコンや照明器具の設置など、いわゆる“家庭内の電気工事”には一通り対応できます。電圧が600V以下であれば、分電盤の増設や回路の改修といった作業も可能です。
しかし、現場が工場やビル、あるいは集合住宅の共用部分などになると事情は変わります。こうした場所には高圧の受電設備が存在することが多く、それに関わる工事は第一種の資格がなければ対応できません。さらに、使用機器が高容量であったり、複雑な配電盤や幹線が絡むような工事では、安全管理や設計の観点でも、より高い知識と判断力が求められます。
また、第一種の資格があることで、工事だけでなく管理的な業務を担うことも可能になります。具体的には、主任技術者として工事全体の安全や品質をチェックする立場になったり、社内での役職登用や元請けとしての案件受注にも有利になるケースがあります。
このように、第一種と第二種では「使える道具」の違いだけでなく、「求められる役割」そのものが異なります。だからこそ、自分が将来どのような立場で働きたいのか、その見通しを持ったうえで資格を選ぶことが重要なのです。次のセクションでは、こうした違いが収入やキャリアパスにどう影響するのかを見ていきましょう。
年収にも差が出る?一種・二種による働き方の違い
資格の違いは、実務内容だけでなく、収入やキャリアの道筋にも影響します。一般的に、第一種電気工事士のほうが対応できる現場が広く、責任ある立場を任されやすいため、給与水準もやや高くなる傾向があります。とくに工場やビルメンテナンス業務、高圧設備の管理を含む職場では、一種を持っていることで手当や役職がつくこともあります。
一方で、住宅工事や小規模施設に特化した事業所では、二種のみで現場を回しているケースも多く、そうした職場では資格による収入差はほとんど出ないこともあります。大切なのは、どのような職場で、どのような働き方を望むのかを明確にすることです。
また、求人情報を見ると、電気工事士の募集要件として「第二種以上」と記載されているものが多数を占めています。これは、現場の実務で最も必要とされているのが、実は第二種のスキルだからです。そのため、資格の上下ではなく「現場のニーズに応えられるかどうか」が評価基準になることも少なくありません。
ただし、将来的に管理職を目指したい、元請けとして自立したいと考える場合は、第一種を取得しておくことが武器になります。施工管理技士や電気主任技術者などの上位資格との連携も視野に入ってくるため、キャリアの幅が一気に広がります。
このように、収入や立場に与える影響は、資格そのものだけでなく、それをどのように活かすかによっても変わってきます。次のセクションでは、第二種から始めて一種を目指すルートについて、現実的な進み方をご紹介します。
まずは実務経験、次に一種。段階的ステップアップのすすめ
初めから第一種を目指すのも一つの方法ですが、現実的には「第二種で現場経験を積みながら、必要に応じて一種を取得する」というステップアップ型の進み方が、多くの技術者にとって無理がなく、確実なルートです。実際、第一種の免状を得るには試験合格だけでなく一定の実務経験(一般的には5年程度)が必要となるため、まず二種を取得し、実務に就くことが合理的な選択肢になります。
現場に出て働くなかで、高圧設備や受変電設備に関わる機会が増えてくると、自然と「この工事には一種が必要」という実感が湧いてきます。こうした実感がある状態での学習は、机上の知識だけで進めるよりも、理解度が深まりやすく、資格取得後の実践力にもつながります。
また、企業によっては、社内のキャリア制度として第二種取得者に対し、講習費用や試験対策支援を用意しているケースもあります。そうした環境をうまく活用すれば、経済的な負担を抑えつつ、ステップアップの準備を進めることが可能です。
さらに、施工管理技士や電気主任技術者などの関連資格との連動を意識すれば、将来の選択肢が格段に広がります。一つの資格に固執するのではなく、経験と合わせて「仕事の幅」を広げていくことが、長期的には大きな武器になります。
無理に一種から始めるのではなく、今できることを確実にこなしながら、必要に応じて次のステップを踏む。この姿勢こそが、電気工事士としての信頼を積み重ねる道です。
→ https://www.murakami-electric.jp/recruit
一種か二種かは、働き方の意思決定とセットで考える
第一種と第二種のどちらを選ぶべきか。それは単なる資格の難易度や業務範囲の比較ではなく、「自分がどう働きたいか」という意思決定とセットで考えるべき問題です。住宅工事に特化して地域で安定的に働きたい人と、大規模な施設で専門性を高めたい人とでは、求められるスキルや経験が異なります。
資格は手段であって目的ではありません。一種にも二種にも、それぞれの現場に応じた役割と価値があります。どちらを選ぶにせよ、学び続ける姿勢と、現場で信頼される技術者であろうとする意識こそが、最も大切な資産になります。
自分の進む道を見極めたい方は、具体的な働き方や環境について、まず話を聞いてみるのも一つの手です。